社会保険労務士さんってどんなお仕事をされているか、ご存じですか?
社会保険労務士の名前は目にすることがあっても、どんな仕事をされているのかわからない方も多いはず。
今回はなんと、北海道社会保険労務士会にインタビューをさせていただき、社会保険労務士のお仕事をうかがってきました。
初歩の初歩からお話を聞いてみたので、「社会保険労務士ってどんな人?」「札幌で社会保険労務士に頼りたいんだけど、依頼の方法がわからない」という方にもオススメです。
では、行ってみましょう。
 マエちゃん
マエちゃん社会保険労務士は、会社やお店の経営者さんや、従業員のかたを仲立ちする心強い存在だということがインタビューでわかったので、ぜひ読んでみてください。
北海道社会保険労務士会でお話を伺ってきました






お話をうかがってきた場所は、札幌市中央区にある北海道社会保険労務士会です。
札幌市営地下鉄の西11丁目駅から徒歩5分ほどのビルにあります。近くにある建物は、中央区複合庁舎やプリンスホテルです。
今回は、北海道社会保険労務士会広報部の社会保険労務士先生方にお話をうかがいました。



多屋美織先生 北海道社会保険労務士会 常任理事 広報部長



川北光晴先生 北海道社会保険労務士会 理事 広報副部長



定蛇萌先生 北海道社会保険労務士会 理事 広報部
社労士って、どんな仕事?



初めまして、本日はよろしくお願いします!
さっそくですが、あらためて基本的なことをお聞きします。「社会保険労務士(社労士)」とは、どんなお仕事をされている方なんでしょうか?



社会保険労務士は、労働と社会保険等に関する法律の専門家です。
たとえば、「会社が従業員を採用し、雇用する」という流れの中で、雇う側には守るべき法律がたくさんあります。
ですが、経営者の方がすべてを自力で対応するのは大変です。そこで私たち社労士が、法律面からサポートを行います。



ほかにも、老後に受け取る「老齢年金」や、病気やケガで障害が残ったときの「障害年金」など、年金制度に関するサポートも仕事のひとつです。
職場でのハラスメント対応なども社労士がご支援できる分野です。



ぼくの考えでは、社労士の仕事は「社会や地域を豊かにすること」だと思っています。
ご依頼くださるのは主に経営者の方ですが、会社には従業員、ご家族、株主、お客様、取引先など、多くの関係者(ステークホルダー)がいます。
ですから、経営者の方の依頼に応えながら、会社で働く人やその先にいる人のことも考える仕事だと思っています。



ありがとうございます!
ひとつ素朴な疑問なんですが……。そもそも、どうして経営者は労働に関する法律を守らなければならないのでしょうか?



会社と従業員の間には「雇用契約」があるので、その点、法律的には対等な関係です。
ただ、歴史的に見ても、会社の立場が強く、従業員が弱い立場に置かれてきた背景があります。
そこで、労働基準法などを整備して、最低限の基準を定めて、従業員が安心して働けるようにした経緯があります。



なるほど!だからこそ、経営者は労働基準法などに従って人を雇う必要があるんですね。
そして、労働に関する法律をサポートするのが社労士さんですか。
他の士業との違いは?



社労士さんのお仕事、少しずつイメージができてきました。
ところで、社労士さんは税理士さんや行政書士さんなど、他の士業の先生とどう違うんでしょうか?



税理士さんはお分かりのとおり、税務の専門家です。行政書士さんは行政手続きの専門家。社労士は、雇用や労働・年金に関する法律の専門家です。
それぞれに担当分野と“独占業務”があります。
たとえば、就業規則の作成は社労士の独占業務です。他の士業が就業規則を作成して提出代行するのは、法律に触れます。(弁護士は除く)



あと、関係する役所も違いますね。私たち社労士がよくやり取りするのは、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所などです



他の士業さんの付き合う役所は違うんですか?



はい。たとえば税理士さんなら税務署。行政書士さんなら道や市など。私達、社労士は労働局(労働基準監督署)、年金事務所、ハローワークなどになります。



まるっと円山
そうなんですね!国家資格を取るための試験も違うんですか?



違いますね。社労士、税理士、行政書士などは、それぞれ別の法律分野について勉強して資格を取ります。毎年、8月に社会保険労務士試験が実施されています。
経営者にとっての社労士のメリットは?



では、社労士の先生に依頼すると、どんな手間が省けますか?



まずは、従業員さんの入退社の手続きがイメージしやすいかと思います。
人を雇うと、ハローワークや労働基準監督署などに書類を提出する必要がありますが、こういった事務手続きを社労士に代行できます。
経営者の方は、本来の仕事に集中できるのが大きなメリットです。



それに、労働・社会保険関連の法律は頻繁に改正されるので、アドバイスができます。
経営者が法改正を知らずにいると、気づかないうちに違法状態になっていることもあるんですよ。



具体的には、どんなケースがありますか?



たとえば、前の話になりますが、2019年に改正施行された労働基準法では、有給休暇について会社は、年10日以上有給休暇が付与される従業員について、年5日以上の有給休暇を取得させるということになりました。
それを、法改正を知らずに、従業員に有給休暇を取らせなかった会社は、労働基準監督署から指導を受けたり、労働基準法では罰則が定められています。
この場合は違反すると、30万円以内の罰金です。



まるっと円山
ええ!?経営者は法改正を見逃すと、大変なことになるんですね。
それをアドバイスしてくれるのが、社労士さんなんですか。
自分でやるより社労士に頼んだ方がいい?



「自分でもできる範囲だから、まだ社労士には頼まなくてもいいかな」という経営者の方もいらっしゃると思います。
それでも社労士に依頼するメリットはありますか?



たしかに、従業員が2〜3人ほどの小規模な会社であれば、最初のうちは経営者ご自身で対応できることもあります。
でも、法律に沿って正確にやるのは、意外と難しいんですよね。



社労士を入れるメリットとして大きいのは、従業員とのトラブル予防につながる点ですね。
たとえば、よくあるのが、「労働時間の管理」の問題です。
「法律で定められた休みは、4週を通じて4日以上必要なのに、実際は従業員に法律どおりの休日を与えていなかった」
「労働時間が1日8時間を超えているのに、割増賃金になってない」
なんて問題が起こりがちです。



今の時代、従業員さんは「うちの会社やお店は法律を守ってるの?」と疑問に感じたら、すぐにPCやスマホで調べられるんです。
「労働基準法に違反してる可能性がある!」とわかると、従業員が労働基準監督署に相談するケースが昔よりも増えてます。一人が声を上げると、他の従業員にも広まりやすいですし、場合によっては裁判に発展することもあります。
そうなれば、弁護士にも依頼が必要になり、さらに費用や手間がかかってしまいます。



実際、経営者の方は、「なんでうちが……」と最初のうちはご理解を頂けないこともあります。
でも、よく調べてみると、「会社側が気づかないうちに違反をしていた」というケースはあります。
日ごろから社労士と一緒に労務管理をしておけば、そうしたトラブルを未然に防げます。



まるっと円山
なるほど。法律も厳しくなってきているし、従業員も情報を得やすくなっている時代です。だからこそ、早めに社労士さんに相談するのが大切なんですね。



「社労士に相談すると、厳しいことばかり言われそう」と思う経営者がいらっしゃるかもしれません。
でも、実は「法律をきちんと守った結果、会社の業績や生産性が良くなった」というケースも多いです。
たとえば、昭和や平成の前半はサービス残業が当たり前でした。私も、前職は会社員でしたが、上の世代の人はそういう考えの人が多かったと思います。



しかし、「法律を守って、決められた時間内で仕事を終わらせよう」と経営者の方と社労士が一緒に取り組むと、「どうすれば時間内で仕事を終わらせられるか?」という視点が生まれます。
経営者と社労士が、業務の洗い出しや見直しをしていくことで、無駄な作業や非効率な流れが見えてきます。その結果、労働時間が短くなっても売上は変わらないということが起こります。
最終的に、利益を増やせて、従業員の給与やボーナスを増やすこともでき、職場環境が良くなって離職率も下がる。そんな良い循環が生まれることもあるんですね。
今までの日本は、長時間労働をよしとする雰囲気がありました。
しかし、生産性を上げるお手伝いができるのも、社労士に頼むメリットだと思います。
飲食店などの小規模事業者へのサポートは?



なるほど!では、飲食店など小規模事業者に対して、社労士の先生はどんなサポートができますか?



まずは書類のサポートですね。
たとえば、雇用契約書や就業規則の作成、助成金申請のアドバイスなど。人を雇う段階から関わることができます。
最近では、最初の段階から社労士に相談される経営者の方も増えてきていますよ。



へー!そうなんですね!



たとえば、ハローワークに出す求人票の確認もできます。
労働法令も複雑化しているので、まずその理解をしないと求人票の提出が難しいということも起きています。
そういうときは、社労士が求人票の書き方をサポートできるんです。



ハローワークの求人票と、民間の求人誌・求人サイトの違いは、そもそも何ですか?



民間企業のサービスは、求人募集を出す時にお金がかかることが多いです。でも、ハローワークは公的機関なので、無料で掲載できるメリットがあります。
ただし、ハローワークの職員さんはとても忙しいので、求人票の内容まで細かくアドバイスをもらえることは少ないんです。
だからこそ、社労士に依頼していただくと、求人の効果的な書き方のお手伝いをすることができるんですよ



なるほど!そういう違いがあったんですね。
助成金と補助金の違い



社労士さんといえば、「助成金の申請をお願いできる」というイメージがあります。
ところで、「助成金」と「補助金」って、何が違うんでしょうか?



助成金は、主に厚生労働省が管轄しているものが多く、人(従業員)に関する制度が中心です。
社労士は、その申請代行ができる国家資格者です。
一方、補助金は、経済産業省などが管轄しているものが多くて、設備やモノへの投資が中心になります。
こちらも社労士は関われますが、税理士さんや中小企業診断士さんなどが関わるケースが多いです。



なるほど、取り扱う役所も違うんですね。



そうなんです。
もうひとつ大きな違いは、助成金は要件を満たせば受け取れることが多いのに対し、補助金は要件以外にも審査があって採択されないともらえないことです。
補助金は書類提出後に審査があるので、採択率は30〜50%程度と言われています。



なるほど!ちなみに、最近ではどんな助成金がありましたか?



コロナ禍で多くの会社さんが申請をしたのが、「雇用調整助成金」ですね。
緊急事態宣言中に、多くの会社やお店が休業や時短営業を余儀なくされました。
その間も、会社は人が辞めないように支払った休業手当などの一部を、国が助成したのが雇用調整助成金(コロナ特例)です。
当時は申請が簡素化されてたんですけど、それでも提出する書類が不十分で、あわてて社労士に頼んだ事業主さんが多かったですね。
助成金は、日ごろから法律通りの書類をきちんと整えておかないと、いざという時に申請できないことがあります。
そういった意味でも、普段から社労士に関わってもらうことが大切です。



なるほど。いざという時のためにも、会社の制度や書類はきっちりする必要があるんですね。
社労士さんとどう繋がればいい?



社労士さんに相談したいと思ったとき、どこで探せばいいんでしょうか?



北海道社会保険労務士会のホームページをぜひ、検索してみてください。
そこから自分に合った社労士を探すのが一番です。
たとえば、ホームページでは、道内の地域やそれぞれの先生の得意分野も載っているので、参考にして問い合わせるのがいいかなと思いますね。



他には、どんな手段がありますか?





北海道社会保険労務士会では「総合労働相談所」という相談窓口を設けています。平日は夕方17時から20時まで。土曜日は13時~16時まで社労士が直接ご相談をお受けしています。
電話又は来所での相談が可能です。(総合労働相談所011-520-1953)
札幌近郊の方は、こちらに来ていただくといいですね。その他にも、「街角の年金相談センター」「社労士会労働紛争解決センター北海道」などの窓口があります。



ほかにも、無料で相談できる窓口はあるんですか?



毎年10月は、社労士制度推進月間として北海道内10支部で無料相談会などのイベントが開かれています。
社労士に頼む費用はどれくらい?



ありがとうございます!ちなみに、社労士さんに依頼すると、どれくらいの費用がかかるものなんでしょうか?



業務内容や、従業員の人数、企業規模などによって大きく変わると思います。
まずは複数の社労士に見積もりをとってみてください。



それと、費用の安さだけでなく、経営者と社労士との信頼関係もすごく大事だと思います。
社労士は継続的にお付き合いすることが多いので、自分と相性がいいと思う社労士さんを見つけてもらえるのがいいですね。
最後に、経営者の方へひとこと



ありがとうございます!
社会保険労務士さんに依頼するのは経営者の方が多いと思うんですね。
最後に、札幌を始めとする地域の経営者の方にメッセージをお願いします。



私はセミナー講師など引受けた際によく言ってるんですけど、今の時代は物価上昇や労務トラブルの増加で、経営者の方にとって難しい時代だと思います。
私たちが学生の頃は、未払いの残業代があっても、ハラスメント事案が発生しても、泣き寝入りが多かったと思います。
けれど、今のみなさんは、先ほども触れた通り、インターネットで調べてきます。
昔に比べて労働紛争は増えているので、事前に社労士に相談してほしいですね。
法律に沿った労務の整備をしておけば、労務問題のリスクを減らせます。「うちはまだ大丈夫」と後回しにせず、今のうちに見直してほしいです。



ありがたいことに、最近は「社労士(社会保険労務士)」という名前が少しずつ知られるようになってきました。
そのおかげで、従業員の方に「顧問の社労士がいる」と伝えると、安心してもらえることがあるようです。
「この会社は自分たちの労務環境をちゃんと整えてくれているんだな」と、一つの指標のように受け取ってもらえているようです。
どうぞお気軽にご相談ください。



私が経営者の方に伝えたいのは、従業員の方々が笑顔でやりがいを持てる、働きがいのある環境を整えると、会社にいろいろなメリットがあるということですね。
従業員が笑顔でやりがいを持って働ければ、家庭や地域社会にもいい影響を与えて、それが巡って会社の業績にも寄与します。
「損して得を取る」ではないですが、会社の職場環境などを整備すれば、確実に業績など会社にとってプラスになって返ってくる可能性が高まると思います。
時代の変化は早いですが、じっくりやることが必要なのかなと思いますね。



なるほど、それぞれの視点の違いがあって、素敵ですね。ありがとうございます!
札幌で社会保険労務士さんへ頼りたい方は、北海道社会保険労務士会のホームページと札幌市中央区の西11丁目駅にある北海道社会保険労務士会事務所へ行ってみてください。
編集後記 社会保険労務士に出会う確率は3,000人に1人
社会保険労務士(社労士)という名前は聞いたことがあっても、その仕事内容までは知らない方も多いでしょう。
人生で学校や仕事を通じて親しく関わる人の数は約3,000人(諸説あり)と言われます。
一方、社労士は全国に約4万5,000人。日本の人口約1億2,500万人で割ると、およそ3,000人に1人という計算です。
言い換えれば、3,000人と出会ってようやく1人の社労士に出会える確率になります。



Facebookで3,000人のお友達がいた場合、約1人が社会保険労務士さんという確率です。
社会保険労務士さんの存在に気づきにくいのも、ある意味で仕方ないのかもしれません。
とはいえ、私たちの多くは会社で働いています。
働きやすい職場環境を整える手助けをしてくれる社労士の存在は、非常に大きな意味を持ちます。
社労士の川北先生も「社労士は会社だけでなく、地域や社会に貢献できる仕事」とお話しされていました。もっと多くの方に、この職業の魅力が伝わることを願わずにはいられません。
北海道社会保険労務士会 広報部の三人の先生方、本当にありがとうございました!
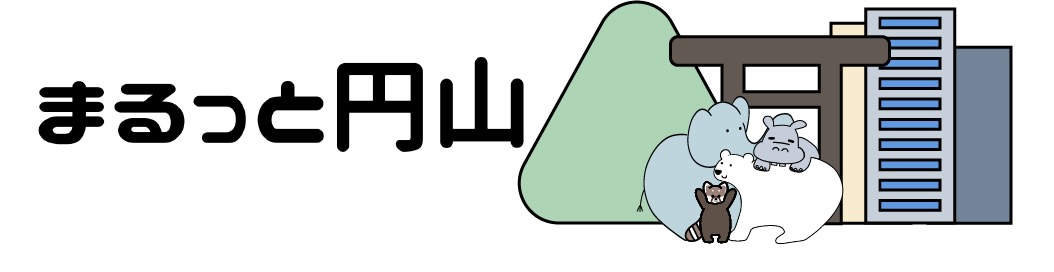
-コピー-1-競合-04-アートボード-32.png)
-コピー-1-競合-04-アートボード-32-300x158.png)
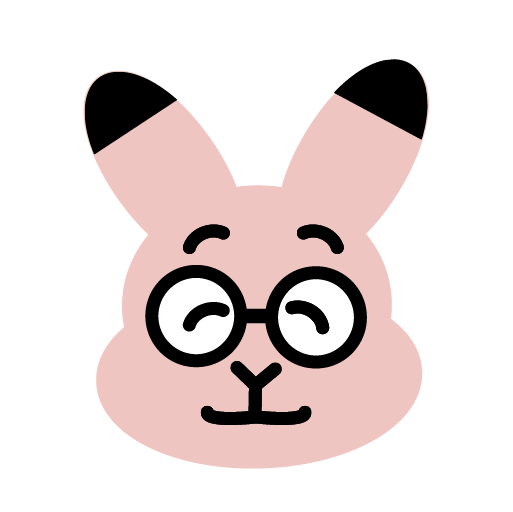
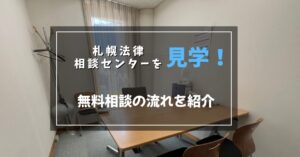
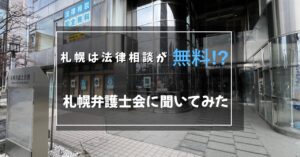






コメント